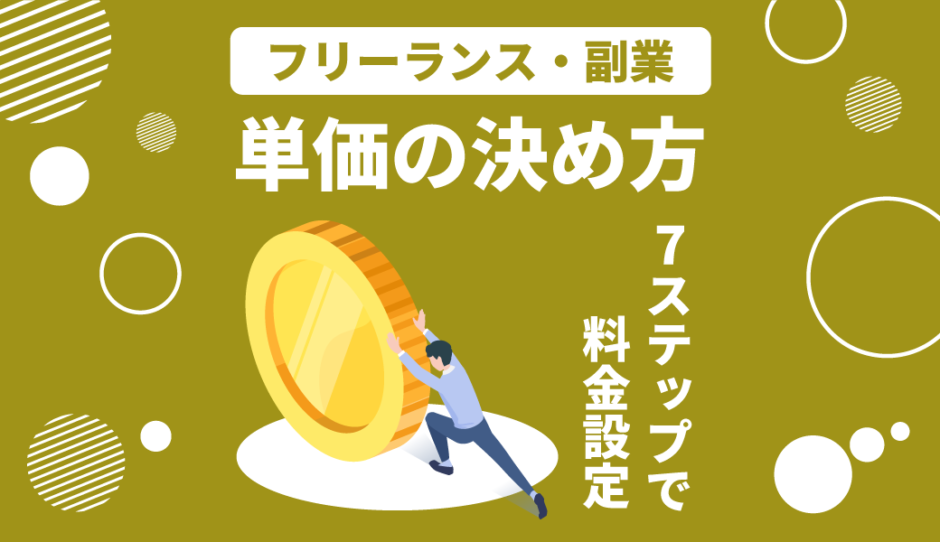当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。
多くの駆け出しフリーランスが最初に悩むのが「自分のスキルやサービスには、いくらの単価をつければいいのか?」ということです。
価格設定は、自分の価値を市場に伝える大切な手段である一方
「安すぎて損をしないか」
「高すぎて仕事が来ないのでは」
「何を基準に決めればいいのか分からない」
と不安を感じる場面でもあります。
フリーランスとして一歩を踏み出すうえで、大きな壁・悩みになりがちです。
本記事では、自信を持って単価・報酬を決められるような考え方を分かりやすく解説していきます。

単価設定って、本当に悩むよね。自分の商品、スキルの価値ってどのくらいだろうって。

最初は誰でも戸惑うポイントね。どうやったら適切な価格設定をできるか解説していきます!

・図解制作や資料デザインの仕事をメインに受注
・ランサーズ:認定ランサーの獲得、実績181件、累計652万円の獲得報酬
・ココナラ:プラチナランク継続、販売実績340件以上で評価★5
フリーランスが自分の単価や報酬をうまく決められないのは、いくつかの共通した原因があるからです。
ここでは代表的な4つの理由を紹介し、それぞれの課題を明確にしていきます。
1. 相場を知らない
最も多い悩みが「相場がわからない」ということ。
自分のスキルやサービスが市場ではいくらで取引されているのかを知らなければ、適正な価格をつけるのは難しいものです。
相場を把握していないと、必要以上に安く受けてしまったり、逆に高すぎて依頼が来なくなる、といった失敗に繋がります。
2. 自分のスキルを客観視できない
自分のスキルや経験をどう評価するかも、悩ましいポイントです。
実績が少ないうちは「自信が持てない」「過小評価してしまう」ことが多く、割に合わない仕事を抱えがちです。
一方で、実力以上に高く見積もってしまうと、クライアントの期待に応えられず信頼を失うリスクもあります。
客観的な視点で自分の立ち位置を理解することが大切です。
3. ターゲットがあいまい
誰に向けてサービスを提供するのか?この「ターゲット」が明確でないと、価格帯も定まりません。
たとえば、個人向けと企業向けでは予算感もニーズも異なります。
中小企業か、大手企業かによっても、期待されるクオリティや価格は大きく変わることもあります。
4. 工数や業務範囲が不明確
サービスにどんな作業が含まれ、どれくらいの時間がかかるのかを把握できていないと、適切な価格設定はできません。
「やってみたら想像以上に大変だった」
「こんなに時間がかかってこの金額は割に合わない」
そんな後悔を防ぐには、あらかじめ業務内容と所要時間を明確にしておくことが必要です。

このような迷いを持ったまま価格を決めようとすると、根拠のない“なんとなく価格”になってしまいがちです。

どれも当てはまるかも…でも理由が整理されると、ちょっと道筋が見えてきた。
単価設定は、勘や感覚で決めるものではありません。
必要な情報を順を追って整理・分析していくことで、納得感のある価格を導き出せます。
ここでは、フリーランスとして自信を持って価格を提示するための7つのステップをご紹介します。
STEP1|相場金額の上下限を調べる
まずは、自分の職種やサービス内容における市場相場を調べましょう。
相場を知ることは、価格が極端に高すぎたり安すぎたりするのを防ぐための基本です。
クラウドソーシングやフリーランスエージェントの案件情報から、似たサービスの「上限」と「下限」の価格帯を調べると良いでしょう。
ざっくりでも構わないので、自分がどのあたりに位置するのかを掴むことが大切です。
STEP2|自分のスキルを棚卸しする
次に、自分のスキルや経験を整理してみましょう。
「何ができるか」だけでなく、「どのレベルでできるのか」「どんな実績があるのか」をできるだけ客観的に言語化してみてください。
過去の成果物や対応した業務、得意分野をリストアップすると、自分の強みや市場価値が見えてきます。
STEP3|ターゲット(想定顧客)を明確にする
誰にサービスを提供したいのか、そのターゲットを明確にします。
なぜなら、顧客によって予算感がまったく異なるからです。
たとえば、個人事業主と大手企業では、求められる成果物のクオリティも、支払える金額も違います。
「どんな人や企業に、どんな価値を届けたいのか」を具体的にイメージしておくことで、現実的な価格戦略が立てやすくなります。
STEP4|業務内容・工数・経費を洗い出す
提供するサービスにどんな作業が含まれているのかを具体的に分解し、それぞれにかかる時間(工数)や必要経費を見積もる。
作業工程ごとの所要時間、使用するツールやソフトの費用、通信費、交通費など、業務にかかるコストはすべて洗い出しましょう。
ここを曖昧にしたままだと、「想像以上に手間がかかってしまった」「利益がほとんど残らなかった」といった事態になりやすいので要注意です。
STEP5|基本となる単価を設定する
STEP1〜4で得た情報をもとに、基本の価格帯を決めていきます。
まずは、相場と自分のスキルレベルから「大まかな価格帯」を設定しましょう。
例えば、その業界のプロレベルなら高価格帯でも問題ありませんが、駆け出しレベルなら低価格帯からスタートするのが良いでしょう。
次に、ターゲットの予算感や工数・経費を踏まえて、決めた価格帯の中で具体的な単価を固めていきましょう。
単価・報酬の提示方法としては、以下3つが一般的です。
- 案件単位の価格(例:この作業一式で5万円)
- 時間単価(例:1時間3,000円)
- 作業単価(例:1文字2円、画像1枚3,000円)
案件の内容や見積もりのしやすさ、クライアントの慣習に応じて使い分けましょう。
STEP6|オプション料金も考えておく
基本の業務範囲が決まったら、追加対応が発生した場合のオプション料金も設定しておくと安心です。
たとえば、次のように明文化しておくとトラブル・すれ違いを防ぎやすくなります。
- 修正料金:修正は2回まで無料、それ以降は1回につき+1,000円
- 特急料金:通常納期は2週間、1週間以内なら追加で+5,000円
ここで、STEP4で洗い出した作業や工数が活きてきます。
追加対応にどれくらい時間や手間がかかるかを把握しておけば、適正なオプション料金も算出しやすくなるからです。
STEP7|最終的にはクライアントとのすり合わせ
こちらで設定した単価が、必ずしもそのまま通るとは限りません。
最終的には、クライアントの予算とすり合わせて調整する必要がある場合も。
とはいえ、単に「下げる」のではなく、こちらが提示した価格の根拠を説明できるようにしておくことが重要です。
相手に納得してもらいやすくなりますし、こちらの信頼感にもつながります。
場合によっては、業務内容を調整することで価格を維持する、という柔軟な対応も視野に入れましょう。

いきなり「いくらにしよう?」って考えても難しいんですよね。だから、こうやってステップに分けて情報を整理していくのがおすすめです。

一つ一つやるのは大変そうだけど、これを全部やれば、自信を持って「この金額です!」って言えそう!
ステップに沿って単価を決めることは大切ですが、それだけでは十分とは言えません。
より納得感のある価格設定にするために、以下の3つの注意点もぜひ押さえておきましょう。
「欲しい金額」だけで決めない
目指す収入をもとに単価を考えるのは大切ですが、それだけで決めてしまうのは危険です。
相場、自分のスキル、ターゲット顧客の予算感といった外部の基準とズレていると、仕事を獲得できない可能性が高まります。
たとえば、実績が少ないうちから相場よりも高い価格を設定してしまえば、クライアントの信用を得るのは難しくなります。
また、個人向けのサービスなのに、企業向けの価格帯を設定すれば、検討すらされないこともあるでしょう。
単価は「自分の理想」だけでなく、「市場で通用するかどうか」も意識して決める必要があります。
スキルや時間を安売りしない
その一方で、自分の価値を低く見積もりすぎるのも問題です。
特に活動初期には「とにかく実績を作りたい」という気持ちから、相場よりもかなり低い価格で受けてしまいがちです。
一時的な戦略として低単価にするのはありですが、ずっと安いままでは疲弊してしまいます。
低すぎると、たくさんの案件をこなさないと生活できず、時間も余裕もなくなり、クオリティが下がるリスクもあります。
さらに、一度安く受けた単価を後から引き上げるのは難しいのも現実です。
「今はこれでいいや」ではなく、将来的に持続できる価格かどうかも考えておきましょう。
単価で収支シミュレーションしてみる
設定した単価が、実際にどれくらいの収入につながるのかをシミュレーションしておくのも重要です。
たとえば、下のように計算してみることで、目標収入を達成するには何件受ける必要があるか、どれくらい働くかが明確になります。
- 案件単価10万円 × 月5件 ⇒ 月収50万円
- 時間単価2,000円 × 月120時間 ⇒ 月収24万円
- 作業単価4,000円/枚 × 月100枚 ⇒ 月収40万円
単価だけでなく、稼働量や営業戦略とのバランスを考えるためにも、収支シミュレーションはとても役立ちます。

「とにかく稼ぎたい!」って気持ちだけで単価を決めちゃうと、長期的に見ると上手くいかなそうだね。

逆に安く受けすぎても、忙しいだけで全然儲からないってなるので、適正な価格を模索することも大切です!
フリーランスとして活動する際、案件単位や成果物単位での報酬設定が一般的ですが、自身の働き方を「時給」に換算してみることもおすすめします。
適切な価格設定や収入のバランスを見直す上で役立ちます。
以下に、会社員から独立した場合や新卒フリーランスの場合など、状況に応じた時給換算の目安をご紹介します。
フリーランスの時給換算の目安はどこ?
会社員からフリーランスに転身した場合、まず比較対象となるのは独立前の給与です。
フリーランスは会社員と異なり、社会保険料の自己負担分が増えたり、福利厚生がなくなったり、仕事が不安定だったりするリスクも考慮に入れる必要があります。
そのため、単純な手取り額だけでなく、これらの要素も加味した上で、会社員時代の給与水準を上回る時給を目指すことが望ましいと言えます。
例えば、会社員時代の年収が500万円だった場合、月収は約41.7万円(500万円 ÷ 12ヶ月)となります。
これを月160時間(1日8時間×20日)働くと仮定すると、時給は約2,600円(41.7万円 ÷ 160時間)となります。
フリーランスとしてはこれ以上の時給を目指すことで、会社員時代の収入水準を維持または上回ることができます。
新卒でフリーランスとして活動を始める場合や、会社員経験が少ない場合は、比較対象となる前職の給与がないかもしれません。
そのような場合は、自分と同じような仕事をしている正社員の給与水準を参考にすると良いでしょう。
例えば、dodaの「平均年収ランキング」によると、2024年のWebデザイナーの平均年収は378万円、SE/プログラマーの平均年収は425万円とされています。
これらを月収に換算すると、それぞれ約31.5万円(378万円 ÷ 12ヶ月)、約35.4万円(425万円 ÷ 12ヶ月)となります。
これを月160時間働くと仮定すると、Webデザイナーの時給は約1,970円(31.5万円 ÷ 160時間)、SE/プログラマーの時給は約2,210円(35.4万円 ÷ 160時間)となります。
案件や作業量によって月収ベースでは平均に届かない場合でも、時給換算で平均を上回っていれば、効率的に働けている一つの指標になります。
日本全体の中央値や平均値と比較する
さらに広い視点を持つために、日本全体の所得に関する中央値と比較してみるのも一つの方法です。
例えば、dodaの「平均年収ランキング」によると、2024年の日本人の年収の中央値は380万円(平均値426万円)とされています。
これを月収に換算すると約31.7万円(380万円 ÷ 12ヶ月)となり、月160時間働くと仮定すると、時給は約1,980円(31.7万円 ÷ 160時間)となります。
これらのデータを参考に、自分の時給が社会全体の中でどの程度の位置にあるのかを把握することも、客観的な判断材料となります。
時給換算は、フリーランスとしての働き方や収入のバランスを見直す上で非常に有効な手段です。
自身のスキルや経験、市場の相場を考慮しながら、適切な時給を設定し、健全なフリーランス活動を目指しましょう。

案件報酬は単価を時給に直してみると、自分の働き方を客観的に見直すのに役立ちます!

頑張ってるつもりでも、時給にすると意外と低いことってあるよね。働き方を効率化するべきかの目安にできるね。
フリーランスとして継続的に活動し、成長していくためには、一度決めた単価にこだわりすぎないことが大切です。
スキルや実績が増えるにつれて、それに見合った報酬を得ようとする姿勢が事業の持続性やモチベーション維持にもつながります。
市場価値は常に変わり、あなた自身も成長していくはずです。
その変化を反映する形で、単価の見直しを図っていきましょう。
継続的な取引がある場合は、以下のようなタイミングで単価交渉を検討できます。
- 契約更新時
- 新しいプロジェクトの提案時
- 成果を評価されたタイミング
このとき重要なのは、「なぜ価格を見直すのか」という根拠を明確に伝えること。
たとえば、これまでの貢献実績や、新たに習得したスキルなどを具体的に示すと説得力が増します。
クラウドソーシングやスキルシェアサービスを使っている場合は、次のような方法で単価アップを実現できます。
- 出品中のサービスの価格を見直す
- 新しい案件への提案時に、希望金額を引き上げる
サービスの質や実績が積み上がっているなら、価格改定も自然な流れです。
「依頼が多すぎて受けきれない」と感じ始めたら、単価アップの好機です。
これは、需要>供給になっている状態であり、価格を引き上げることで次のようなメリットがあります。
- より良質な案件に集中できる
- キャパシティをコントロールしやすくなる
- 価格でクライアントを“ふるい分け”できる(スクリーニング効果)

フリーランスとして続けるなら、やっぱり単価も上げていきたいですよね。スキルに合わせて、報酬もステップアップしていくのが理想です。

ずっと同じだと、モチベーションも下がっちゃいそう。依頼が増えてきたら、見直すタイミングなんだね!
関連記事:単価交渉のコツやタイミングを詳しく解説!
 【例文付き】フリーランスの単価交渉のコツ&タイミングを知って目指せ報酬アップ
【例文付き】フリーランスの単価交渉のコツ&タイミングを知って目指せ報酬アップ フリーランスの単価設定に関して、多くの方が感じる疑問や不安にお答えします。
Q. 安くした方が案件は取れますか?
確かに、相場より安い価格を提示することで、特に実績が少ないうちは案件を取りやすくなることがあります。
実績作りやポートフォリオ強化のために、あえて価格を下げる戦略も一つです。
ただし、低単価が続くと、「忙しいのに稼げない」という状態に陥ったり、後から単価を上げづらくなったりするリスクがあります。
安さだけを求めるクライアントが集まりやすくなる点にも注意が必要です。
価格を抑える場合でも、「何のために・どの期間だけ」と目的をはっきりさせ、将来的には見直す前提で進めることが大切です。
Q. 単価を安くしてほしいと値切られたら?
値下げ交渉はよくある場面ですが、まずはその単価にどんな根拠があるのかを丁寧に説明するのが基本です。
スキルや作業量、これまでの実績など、価格の理由を伝えることで、納得してもらえる場合があります。
もし予算に折り合いがつかない場合は、価格を下げる代わりに業務内容や納品仕様を調整する提案も検討してみましょう。
たとえば、「この範囲までなら〇〇円で対応可能です」といった形です。
やり取りの内容は、後々のトラブルを避けるためにも、書面やメールで記録しておくのがおすすめです。
なお、あまりに無理な条件を提示された場合や、価格だけで判断されてしまうような取引であれば、無理に受ける必要はありません。
断ることで、自分の価値や働き方を守ることにもつながります。
関連記事:仕事を断ることが苦手な人はこちら ↓
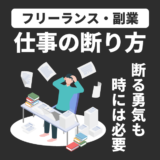 【例文・注意点つき】フリーランスの仕事の断り方・断るべきケースを解説
【例文・注意点つき】フリーランスの仕事の断り方・断るべきケースを解説 フリーランスにとって、単価や報酬の設定は避けて通れない重要なテーマです。
適切な価格を決めることは、働きがいや収入の安定、そして事業の継続にも直結します。
この記事では、単価設定に迷う理由から、価格を決めるための7つのステップ、注意点や時給換算の視点、さらには単価アップの考え方までを解説してきました。
ここで、ポイントを振り返っておきましょう。
これらを一つずつ実践していけば、必ず「納得できる単価」に近づいていけるはずです。

フリーランスの単価は、一度決めて終わりではなく、経験やスキルに応じて見直していくのが大切です。

モヤモヤしていた単価の決め方が、少し見えてきました。まずはスキルを書き出して、相場を調べてみます!