当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。
フリーランスを目指すうえで、自由な働き方の魅力を感じる一方で、

フリーランスとしてずっと続けていけるだろうか?

安定した収入を得ることはできるだろうか?
といった将来への不安を抱えることもあるのではないでしょうか。
実際、スキルがあっても収入が伸び悩んだり、仕事の方向性に迷ったりする人は少なくありません。
そうした不安を乗り越えて、フリーランスとして長く安定して活動を続けるには、「働き方」ではなく「事業」としての視点を持つことが不可欠です。
あなたは単なる「働き手」ではなく、自身の事業を経営する「個人事業主」なのです。
指示された業務をこなすだけではなく、事業の方向性決定から営業、経理、スキルアップまで、全てを自分で舵取りする必要があります。
安定した収入と成長、そして理想の働き方を続けていくには、明確な「事業視点」を持つことが欠かせません。
そこで本記事では、フリーランスが事業主として持つべき7つの重要な視点を解説していきます。

・図解制作や資料デザインの仕事をメインに受注
・ランサーズ:認定ランサーの獲得、実績181件、累計652万円の獲得報酬
・ココナラ:プラチナランク継続、販売実績340件以上で評価★5
フリーランスとして長く活動していくためには、現在のスキルや仕事内容だけでなく、常に未来を見据えた視点を持つことが不可欠です。
なぜフリーランスは将来性・継続性を考える必要があるのか?
フリーランスを取り巻く市場や技術は、驚くほどのスピードで変化しています。
特に近年では、生成AIの急速な発展が多くの分野に影響を与え始めており、これは決して他人事ではありません。
もしあなたの収入が、特定のスキルや限られた業界の需要に大きく依存している場合、その市場が縮小したり、技術の進化によって需要がなくなったりすれば、収入は一気に不安定になるリスクを抱えています。
いわば、1本柱に頼る状態は危険であるということです。
だからこそ、時代の変化を捉え、自身のスキルや事業内容を継続的にアップデートしていく必要があります。
将来の変化に備えた行動こそが、長期的なキャリアの安定、ひいては持続的な収入確保へと繋がるのです。
フリーランスとして将来性・継続性に向けた行動
では、将来を見据えて具体的に何をすべきでしょうか。
基本となるのは、自身の専門分野や関連市場のトレンド分析です。
業界ニュースサイトや専門メディアのチェックはもちろん、信頼できる専門家のSNS発信、あるいはクラウドソーシングサイトでどのような案件が増減しているか、といった身近な情報からも動向は掴めます。
集めた情報をもとに、今後需要が伸びるスキルと、逆に陳腐化・代替されそうなスキルを見極めることが肝心です。
現状維持は後退と同じと考え、必要であれば新しい分野を学ぶリスキリング(学び直し)も視野に入れましょう。
自分が伸ばしていくべきスキルを見極めたら、継続的なスキルアップ計画を立て、実行に移します。
「いつまでに、何を、どのレベルまで習得するか」具体的な目標を設定し、オンライン講座、書籍、セミナー、コミュニティへの参加などを通じて学びを深めていくことが大切です。
スキルだけでなく事業モデル自体にも柔軟性を持たせることを検討しましょう。
例えば、単発のクライアントワークだけをしていた場合。
ブログ収益、オンライン教材の販売、月額課金制のコミュニティ運営など、一度仕組みを作れば継続的な収入が見込めるストック型ビジネスに挑戦するのも1つの戦略です。

今のスキルでずっと食べていけるか、正直ちょっと不安。生成AIとかもすごいし…

時代の変化に対応できるよう、常にアンテナを張って学び続ける姿勢が、将来に繋がります。

「生成AIに仕事を奪われる」ではなく、「自分の仕事にどう生成AIを活用するか」という視点が大切です。
数多くのフリーランスの中から選ばれ、継続的に仕事を獲得していくためには、他者との違いを明確にし、自身の価値を正しく伝えることが重要です。
「誰でもいい」のではなく、「あなたにお願いしたい」と思わせる何かが必要となります。
なぜフリーランスは差別化・ポジショニングが必要なのか?
フリーランス市場は働き方の多様化とともに拡大し、多くのワーカー(副業も含めて)が存在します。
特にオンラインで完結する仕事は、地域を問わず競争相手がいる状況です。
このような環境下で、もし他者と同じようなスキルやサービスを提供しているだけでは、クライアントは価格で比較検討しやすくなります。
その結果、厳しい価格競争に巻き込まれて疲弊するリスクがあるのです。
差別化とは、単に目立つことではありません。
自身の持つ独自の価値をクライアントに正しく認識してもらい、適正な価格かつ納得感を持って選ばれるための重要な戦略です。
フリーランスが差別化をするための戦略
差別化を実現するためには、以下の点を具体的に考えていきましょう。
USP(USP: Unique Selling Proposition)とは「独自の売り」のことです。
スキルはもちろん、職務経験、特定分野での実績、あるいは丁寧なコミュニケーションや迅速な対応といった人柄や仕事の進め方も強力なUSPとなり得ます。
スキルを複数掛け合わせることで独自の価値を生み出すことも可能です。
徹底した自己分析を行い、USPを書き出しましょう。
「誰に対して価値を提供したいのか」を具体的に設定することで、どのような商品やサービスを提供していくか見えてきます。
万人受けを狙うのではなく、特定のニーズを持つ層に深く刺さる存在を目指しましょう。
営業や提案、スキル販売をする際にもペルソナの設定によって、メッセージ性が強まり専門性も際立ちます。
明確にした強みとターゲット顧客をもとに、ポジショニング戦略を練りましょう。
これは「どの市場(業界や分野)で、どのような価値を提供する存在として認識されたいか」を定めることです。
例えば、自分が「私は仕事が早いデザイナー」とアピールするだけではなく、実際に周りの人たちから「Aさんは仕事が早いデザイナー」と思われる必要があります。
競合の動きも意識しながら、自分が輝ける独自のポジションを獲れるようにスキルを発揮していきましょう。
ポートフォリオとは、過去の制作実績や仕事の成果からあなたのスキル・経験をアピールするものです。
単に制作実績を並べるだけでなく、どのような課題に対し、どう貢献し、どのような成果を出したのか、具体的なストーリーや数値を交えて示しましょう。
顧客の声などを掲載するのも有効です。
また、ペルソナの需要やポジション戦略から逆算して、ポートフォリオに載せる成果を絞っておくと効率的です。
クライアントからの相談時にスキルのミスマッチを減らすことができます。
SNSやブログなどを活用し、専門知識や仕事への考え方、人となりを発信することも効果的です。
あなたという「ブランド」を構築し、潜在的な顧客との信頼関係を築くことができます。
SNSの投稿やブログ記事から、「あなたにぜひお願いしたい」と考えてくれる顧客・ファンを増やせる可能性があります。

どうやって仕事を取ればいいのか…。安くしないと仕事来ないかなって思っちゃうよね。

大切なのは「あなたならではの強み」を見つけて、それを求めている人にしっかり伝えることです!
フリーランスとして安定した活動を続ける上で「収益性」について考えることは避けて通れません。
適切な単価や報酬を設定し、利益を確保することは事業の生命線と言えます。
なぜフリーランスは単価、収益性を考える必要があるのか?
会社員の副業収入とは異なり、フリーランスの収入は生活資金や事業を継続するための資金に直結します。
十分な収益がなければ、安心して生活もできませんし、事業活動を続けることも困難です。
特に注意したいのが、安易な「安請け合い」です。
実績作りのために一時的に単価を抑える戦略もあります。
ただし、恒常的に低い単価で仕事を受けてしまうと、長時間働いても十分な収入が得られず、心身ともに疲弊します。
提供するサービスの質の低下を招いて、結果的に事業の継続を危うくする可能性すらあります。
また、新しいスキルを学ぶための自己投資や効率的に仕事を進めるためのツール導入、事業拡大のための外注など未来への投資を行うためにも適切な利益の確保は不可欠なのです。
フリーランスが収益性を高めるためにすべきこと
では、収益性を高めるために具体的に何をすべきでしょうか。
市場の相場を調査することは大切ですが、相場通りの価格をただ設定するだけでは足りません。
「なぜこの価格なのか?」という明確な値付けの根拠を持つことが重要となります。
提供できる価値を客観的に評価し、自信を持って価格を提示しましょう。
周りよりもスキルが高く実績も多ければ、価格設定は高くても売れる可能性が高いです。
逆に駆け出しフリーランスであり、実績が欲しい場合はいったん相場より安い価格で勝負するのが無難でしょう。
スキル、経験、実績に見合った報酬とその理由を説明できるように準備しておくことは、価格交渉でも役立ちます。
また、価格交渉する場合は自分の希望の報酬額を伝えるだけではいけません。
相手の予算や事情も考慮しつつ、例えば提供する業務範囲を調整するなど、双方にとって納得のいく着地点を探る姿勢も求められます。
今より高単価の案件を獲得したい場合は、専門性と解決策を伝える提案力を磨きましょう。
クライアントが抱える課題を理解し、期待を超える解決策を提示できれば、予算から多少離れても交渉に応じてくれることも少なくありません。
加えて、収入源を複数化することも、フリーランスの収入の安定性を高める上で1つの戦略です。
特定のクライアントや単一のサービスに依存する状態はリスクが伴います。
複数のクライアントと取引する、異なる種類のサービスを提供する、ストック型の収入を構築するなど、収入の柱を複数持つことを目指しましょう。
売上から経費を差し引いたものが手元に残る利益です。
どれだけ売上(キャッシュ)があっても、支出(フロー)が多ければ、事業は立ち行かなくなります。
会計ソフトなどを活用し、月の売上と経費を踏まえた利益の状況を常に把握しておくことが大切です。
売上に対して経費が大きくないか、削減できる経費はないかチェックして手元に残るお金を増やしましょう。

単価ってどうやって決めたらいいのか、悩むよね。安すぎてもキツイし、高すぎると仕事が来ないかもって。

市場の相場を軸として、自分のスキルレベルや顧客のペルソナをもとに設定していくと良いです!

例えば、スキルレベルが高くて企業向けであれば高単価。スキルレベルを並み程度で個人向けの場合は低価格から始めると安心です。
関連記事:単価の決め方・単価交渉で迷ったら
 フリーランスの単価・報酬の決め方|7ステップで適切な料金設定
フリーランスの単価・報酬の決め方|7ステップで適切な料金設定
 【例文付き】フリーランスの単価交渉のコツ&タイミングを知って目指せ報酬アップ
【例文付き】フリーランスの単価交渉のコツ&タイミングを知って目指せ報酬アップ
フリーランスとして活動する上で、自由・やりがいといった魅力的な側面だけでなく、潜んでいるリスクにも目を向けて備えておく必要があります。
特に「お金」に関するリスク管理は、事業を安定的に継続させるための土台となります。
なぜフリーランスはリスク管理をするべきなのか?
フリーランスの廃業理由として常に上位に挙げられるのが資金繰りの悪化、すなわちキャッシュフローの問題です。
売上があっても、入金サイクルや経費の支払いタイミングによっては、手元の資金が不足する事態に陥りかねません。
また、フリーランスは基本的に「自分自身が唯一の稼働資産」です。
会社員のように有給休暇や傷病手当金といった保障はありません。
もし、予期せぬ病気や事故で働けなくなれば、収入は即座に途絶えてしまう脆弱性を抱えています。
さらに、税金や社会保険に関する知識不足も大きなリスクです。
確定申告を怠ったり、内容に誤りがあったりすれば、延滞税や加算税といった追徴課税を受ける可能性があります。
また、2023年10月から開始されたインボイス制度への対応など、知らなかったでは済まない制度も存在します。
適切な知識を持つことは、無用な損失を避けるために不可欠です。
フリーランスのお金に関するリスク管理
では、これらのリスクにどのように備えればよいのでしょうか。
具体的な対策を「キャッシュフロー」「会計・税務」「保険・積立」の3つの観点から見ていきましょう。
事業とは別に生活費の最低3ヶ月分、できれば6ヶ月分程度の現金を「緊急用資金」として確保しましょう。
普段使いの口座とは分け、ネット銀行の普通預金などに置いておくのがおすすめです。
売掛金の回収遅延などで一時的に資金が不足しそうな場合、消費者金融を利用するのではなく、ファクタリング(請求書買取サービス)の利用も選択肢の一つです。
ただし、手数料が発生するため利用は慎重に検討しましょう。
事業を始める際や運営において、仕入れや家賃などの固定費がなるべくかからないビジネスモデルを選ぶ。
あるいは、「小さく始める」ことを心がけるのもキャッシュフローを安定させる上で有効です。
一度たまたま失敗しただけで、取り返しがつかなくなるような挑戦は避けましょう。
日々の売上や経費を記録し、事業の収支状況を正確に把握することが基本です。
クラウド会計ソフトを導入すれば、簿記の知識が少なくても比較的に簡単に効率的に会計管理できます。
損益(PL)だけでなく、キャッシュフローの状況もグラフ等で可視化しやすく、改善計画を立てやすいです。
確定申告は、最大65万円の所得控除が受けられる「青色申告」を選択することをおすすめします。
複式簿記での記帳が必要ですが、これも会計ソフトを活用すれば比較的簡単に対応可能です。
また、インボイス制度への対応(適格請求書発行事業者の登録要否、消費税の納税義務が生じた場合の簡易課税制度・本則課税の選択)も検討する必要があります。
フリーランスが支払うべき主な税金・社会保険料には、所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金保険料があります。
売上規模によっては消費税や個人事業税も発生します。
どの税金をいつまでに払わないといけないか把握して、計画的に資金を準備しておく必要があります。
フリーランスには会社のような退職金制度がありません。
老後資金の準備として、iDeCo(個人型確定拠出年金)や個人事業主のための退職金制度である小規模企業共済(掛金が全額所得控除になるメリットあり)への加入を検討しましょう。
病気やケガで長期間働けなくなった際の収入減に備えるため、就業不能保険や所得補償保険への加入も有効なリスクヘッジです。
万が一に自分が働けなくなったとしても、収入が完全には途絶えないよう対策を講じておくことも重要です。
ストック型のビジネス(アフィリエイト、コンテンツ販売、サブスクリプションなど)を取り入れることも、長期的な視点で検討すべき戦略でしょう。

フリーランスは、税金とか保険とか会社員時代は会社がやってくれてたことを全部自分でやらないといけないんだね…

お金周りのリスク管理は事業や生活を続ける上で本当に大切です。特にキャッシュフローと税金の知識は必須!
フリーランスという働き方を選ぶ大きな動機の一つに、「自由度の高さ」を挙げる人は少なくありません。
働く時間や場所を自分で決められることは、確かに大きな魅力です。
しかし、その「自由」を持続可能なものにするためには意識的な努力が求められます。
なぜフリーランスは「働きやすさ」を考える必要があるのか?
自由であるということは、裏を返せば「制限がない」ということでもあります。
明確な就業規則や定時がないため、気づけば際限なく仕事をしてしまう状態に陥ってしまうケースは少なくありません。
心身のエネルギーを過剰に消耗させ、やがて燃え尽き症候群(バーンアウト)を引き起こす原因ともなり得ます。
心や体の健康を損なってしまえば、当然ながら仕事のパフォーマンスは低下します。
集中力が続かずミスが増えたり、納期に間に合わなくなったりすれば、クライアントからの信頼を失い、結果的に収入減や仕事の機会損失に繋がってしまうでしょう。
「働きやすさ」の追求は単なる休息なだけではなく、生産性を維持・向上させ、フリーランスとして長く活動し続けるための重要な戦略です。
フリーランスが「働きやすさ」を保つ方法
では、働きやすさを実現するために、具体的に何をすべきでしょうか。
「1日に何時間働くか」「週に何日休むか」
「どのような場所で働きたいか」「どのような仕事に時間を使いたいか」など
具体的な数値、イメージで自身の希望や価値観を明確にしておくことが大切です。
やるべきことを整理し優先順位をつけるタスク管理の癖をつける。
また、タスク管理の一環として「仕事を断る勇気」も大切です。
自分のキャパシティを超えた仕事量を引き受けたり、条件の合わない依頼を安易に受けたりすることは、働きやすさを著しく損ないます。
自身の限界を把握し、健全な範囲で仕事量をコントロールしましょう。
自宅で仕事をする場合は、仕事スペースを生活空間と明確に分ける。
あるいは、仕事を開始する時間と終了する時間をあらかじめ決めておく。
休日には仕事の通知をオフにするなど、自分なりのルールを設けることが有効です。
仕事スペースでは快適に仕事ができるように長時間座っても疲れにくい椅子を選ぶ、充分なスペックのPCを購入する、といった自分自身が気持ちよく働ける環境づくりも心がけましょう。
また、切り替えが苦手な人は、コワーキングスペースの利用なども選択肢の一つです。

仕事すればするほど利益になるなら、逆に際限なく仕事しちゃいそう。休むタイミングを見つけるのが難しいね。

フリーランスあるあるね!しっかり休むことも、長く続けるためには大事な仕事の一部と考えましょう!
関連記事:仕事の断り方で困っていたらチェック
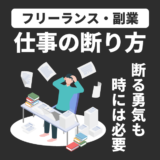 【例文・注意点つき】フリーランスの仕事の断り方・断るべきケースを解説
【例文・注意点つき】フリーランスの仕事の断り方・断るべきケースを解説
フリーランスとして安定的に活動していくためには、質の高い仕事を提供するスキルだけでは足りません。
自ら仕事を生み出し、人との繋がりを広げていく力も重要です。
なぜフリーランスに人脈・営業力が必要なのか?
会社員とは異なり、フリーランスには自動的に仕事が割り振られる環境はありません。
基本的に、自ら行動を起こさなければ新たな仕事を得ることは難しいのが現実。
「待ち」の姿勢だけのフリーランスの収入は、不安定になりがちです。
継続的に案件を獲得し、安定した事業基盤を築くためには能動的な営業活動が不可欠となります。
単に仕事を探すだけでなく、自分の価値を潜在的なクライアントに伝え、関係性を構築していくのがフリーランスの営業活動です。
また、人との繋がりは直接的な仕事の紹介だけではありません。
貴重な情報交換、新しいスキルの習得のきっかけ、クライアントとの協業など、予期せぬチャンスやビジネスの拡大に繋がることもあります。
良好な人間関係は、フリーランスにとって重要な資産の一つと言えるでしょう。
フリーランスが実践すべき人脈づくり・営業
では、人脈と営業力を高めるために、具体的に何をすれば良いのでしょうか。
「営業」と聞くと、直接的な売り込みをイメージするかもしれませんが、方法はいろいろあります。
- 過去の取引先や知人に声をかける「直接・紹介営業」
- SNSやブログで自身の専門性や実績を発信する「プル型営業」
- 「フリーランスエージェント」の活用
- 「クラウドソーシングサイト」での応募・提案
自分の性格や提供するサービス、ターゲットとする顧客層に合わせて、続けやすい方法を探しましょう。
また、自身のスキルや実績を分かりやすく魅力的に伝える「提案力」も磨く必要があります。
クライアントが抱える課題に対して、自分のサービスがどのように貢献できるのかを具体的に示しましょう。
ポートフォリオを効果的に活用したり、相手のニーズを的確に捉えた提案書を作成したりするスキルが求められます。
オンライン:SNSでの交流、専門コミュニティへの参加、オンラインイベント
オフライン:交流会、セミナー、勉強会への参加
といった機会を活用して人脈を広げていくのも大切です。
ただし、単に名刺交換の数を増やすのではいまいちです。
相手に価値を提供したり、継続的にコミュニケーションを取ったりすることで、信頼に基づいた関係性を築くことを目指しましょう。
一度きりの取引で終わらせず、リピーターになってもらう・新たなクライアントの紹介に繋がる可能性を高めましょう。
それには、期待以上の成果を提供すること、丁寧なコミュニケーション、納期を守る、報告・連絡・相談を怠らないなど当たり前のことを当たり前できることが求められます。
一つ一つの仕事を丁寧にこなして顧客満足度を高めることは、継続的かつ安定的な収入に繋がります。

営業って苦手意識があるんだよね。人付き合いも、正直あまり得意な方じゃなくて…

自分に合ったやり方を見つけるのが大切よ!個人的にはクラウドソーシングサイトで出品、提案応募から始めるのがオススメです。
関連記事:在宅ワークの探し方・案件獲得の方法で迷ったら
 在宅で稼ぐ!副業・フリーランスの仕事の探し方を解説
在宅で稼ぐ!副業・フリーランスの仕事の探し方を解説
フリーランスとして日々の業務に追われる中、ふと「自分は何のためにこの仕事をしているのだろう?」と感じる瞬間があります。
単に収入を得るためだけでなく、自分の仕事と社会との繋がりを意識すること。
これは、モチベーションの維持や新たなビジネスチャンスの創出に繋がる視点となります。
なぜフリーランスは社会との接点を考えることが有効なのか?
自分の仕事が誰かの役に立ち、社会が抱える何らかの課題解決に貢献している。
そう実感できることは、仕事に対する意義や目的意識を高め、日々の仕事への大きなやりがいとなります。
これは、困難な状況に直面した際の踏ん張りや長期的なモチベーション維持に不可欠な要素です。
また、環境問題や地域活性化、教育格差、働き方改革など社会が抱える課題は多岐にわたります。
そこに響くサービスや価値を出せれば、時代のニーズを的確に捉えられるのです。
このような事業・仕事は時流に乗りやすく、安定性や成長性の面でも有利になる可能性があります。
さらに、自身の仕事の背景にある想いや社会課題への取り組みを発信することは、それに共感する人々を引き寄せる力もあります。
スキルや価格だけでなく、「あなたの考え方に共感するから」「応援したいから」という理由で選ばれるようになる。
それは強力な差別化となり、熱心なファンや長期的なクライアント獲得に繋がります。
フリーランスが社会と接点を持つ方法
では、社会との接点を持ち、それをビジネスに活かすにはどうすればよいのでしょうか。
自分の仕事が社会のどのような課題解決に繋がっているか、あるいは解決の糸口になる可能性はないか。
という視点で深く考えてみてください。直接的な貢献でなくともOKです。
間接的に誰かの活動を支援していたり、社会をより良くする流れの一部を担っているか連想、分析してみましょう。
何を解決しているかイメージできればモチベーションが上がるだけでなく、事業の成長や展開のアイデアにもつながります。
例:情報セキュリティ研修資料のデザイン
→ 図解で攻撃フローを可視化 → 受講企業の漏えいインシデントが減少 → 個人情報が守られ、デジタル社会全体の信頼性が向上
例:プログラミング講座の開設
→ 小中学生向け Scratch/Python 授業 → 子どもの論理的思考力が向上 → STEM人材の裾野を拡大
SDGs(持続可能な開発目標)に代表されるような社会的な潮流と自分の事業を結びつけてみましょう。
例えば、地域の事業者を支援するサービスを提供する、教育機会の提供に繋がるコンテンツを作成するなど。
社会課題ほど大きな事柄でなく、身近なスケールでもOKです。
住んでいる地域、友人や家族が抱える課題と自分の事業・専門性とに接点がないか探してみてください。
どこに接点があるか意識することで顧客のペルソナが明確になったり、潜在顧客が見えてきます。
「フリーランスとして、自分はどのような価値を社会に提供したいのか」
「自分は事業で何を成し遂げたいのか」
などを明確にすることで活動の軸が定まり、日々の意思決定の指針となります。
自分の目的や存在意義を内省することで、あらたなビジネスチャンスや事業内容を思いつくこともあります。
ブログやSNS、ポートフォリオなどを通じて、「なぜその仕事に取り組むのか」「どのような社会を目指しているのか」を語ることで、共感者・理解者を得ることもできるでしょう。

毎日の仕事に追われていると、本当に社会の役に立てているのか 分からなくなるよね。

まずは、自分の仕事と社会の繋がりを少し意識してみましょう。どんな仕事も必ずどこかで誰かの役に立っているはずです!

試しに直近の案件を3つ挙げて、“誰のどんな課題を解決したか”を書き出してみてください!
ここまで、フリーランスとして細く長く、そして安定して活動を続けていくために重要な7つの視点について解説してきました。
- 将来性と継続性: 変化に対応し、学び続ける
- 差別化とポジショニング: 「あなたに頼みたい」理由を作る
- 単価戦略: 価値に見合った価格で、収益性を高める
- リスク管理: お金と健康の備えで、事業を守る
- 働きやすさ: 自分らしいワークライフバランスを実現する
- 人脈と営業力: 自ら仕事を生み出し、繋がりを広げる
- 社会課題との接点: やりがいを見出し、共感を呼ぶ
これらは独立したものではなく、相互に影響し合っています。
フリーランスという事業を経営する上で、これらの視点をバランス良く持つことが重要です。
すべてを一度に完璧にこなす必要はありません。
大切なのは「自分は事業主である」という意識を持ち、これらの視点を念頭に置くこと。そして、できることから一つずつ行動に移し、試してみることです。
フリーランスを取り巻く環境も、あなた自身の状況も変化し続けます。
だからこそ、定期的に自身の戦略を見直し、アップデートしていくことが不可欠です。

7つの視点、どれも大事なことばかりだね。全部を意識するのは大変そうだけど、まずは頭に入れておく!

「私は事業主なんだ」という意識を持って、できることから少しずつ試していくのがポイントです!




