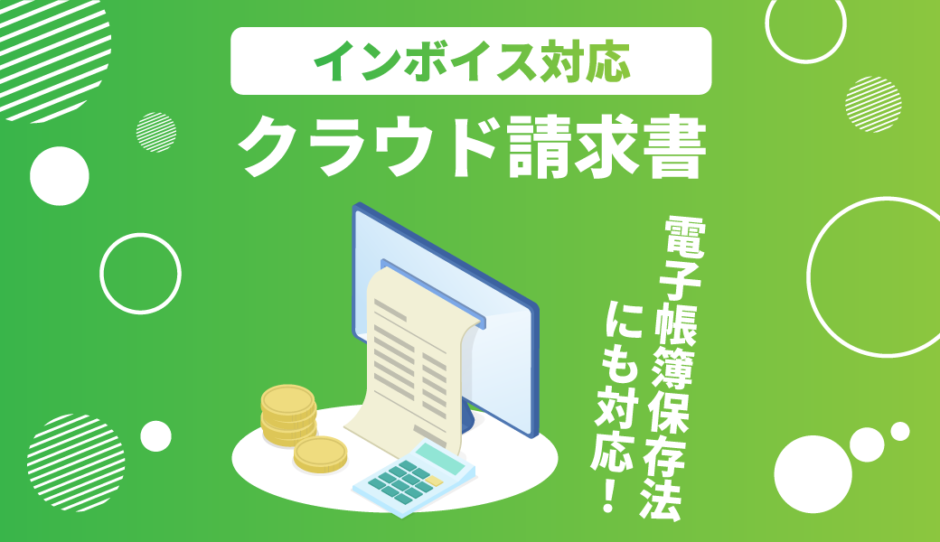当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。
フリーランスとして新たなキャリアをスタートさせたものの
請求書ってどう作ればいいの?
インボイス制度の対応って何から始めればいいのか分からない
そんな不安を抱えていませんか?
請求書の作成や管理は、フリーランスとして報酬を受け取るために欠かせない業務です。
しかし、いざ自分でやってみようとすると、形式や記載項目、保存方法など、意外と戸惑うポイントが多いものです。
さらに、2023年10月からは「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が始まり、請求書業務を取り巻く環境は大きく変わりました。
適格請求書(いわゆるインボイス)を発行するかどうかによって、請求書の書き方や管理の仕方も変わってきます。
今やすべてのフリーランスにとって、インボイス制度は無視できない存在です。
- 請求書の基本的な作り方
- インボイス制度への対応ポイント
- 作業を効率化するクラウドサービスの活用法
本記事では、これらを初心者の方にも分かりやすく、丁寧に解説します。
請求書に関する不安がスッキリ解消され、自信を持って実務に取り組めるようになるはずです。

請求書って最初は戸惑いますよね。お金に関わる分、ちゃんとできるか不安になるのは何もおかしくありません。

僕も“請求書ください”と言われて、慌てて調べました。インボイス制度もあって、ややこしく感じますよね。
フリーランス初心者が請求書業務でつまずかないためには、クラウド請求書サービスの活用が最もおすすめです。
Excelなどで自作する方法もありますが、インボイス制度への対応やミスの防止、請求書の一元管理という点で、クラウドサービスの方が圧倒的に効率的・安心です。
実際、私もフリーランスになりたての頃は、無料のExcelテンプレートを使って請求書を作っていました。
ですが、インボイスの記載漏れや計算ミスへの不安、請求書の管理方法に手間を感じるようになり、最終的に「Misoca」を導入。
会計ソフトとも連携でき、業務の負担が一気に軽減されました。
「Misoca」「freee請求書」「マネーフォワード クラウド請求書」などの主要クラウドサービスには、以下のようなメリットがあります。
- インボイス制度に対応
→ 必要項目が自動で揃ったテンプレートで、誰でも簡単に適格請求書を作成可能。 - 計算ミス・入力ミスの防止
→ 税率や合計金額は自動計算され、ヒューマンエラーを大幅に削減。 - 請求書の発行から保管まで一元化
→ 作成・送信・保存・郵送代行まで、すべてクラウド上で完結。 - 法改正にも自動で対応
→ 制度変更があっても、最新のフォーマットに自動アップデートされて安心。 - 無料プランで気軽に試せる
→ 多くのサービスは無料プランがあり、コストをかけずに始められます。
もちろん、Excelで自作する方法もありますが、確認や管理の手間はどうしても増えてしまいます。
この記事を読み進めることで、あなたに合った方法がきっと見つかるはずです。

結局、請求書はクラウドサービスで作るのが一番ラクです!

クラウドって難しそうと思ってたけど、無料で始められるのもあるんだね。
インボイス制度の開始により、フリーランスも「適格請求書発行事業者」として登録すべきかどうか、判断が必要になりました。
登録するかどうかは、今後の取引や請求書の書き方に大きく関わってくるため、制度の内容を正しく理解しておくことが重要です。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、2023年10月から始まった、消費税の「仕入税額控除」に関する新しいルールです。
「仕入税額控除」とは、仕入れなどで支払った消費税分を、売上にかかる消費税から差し引いて納税額を軽減できる制度です。
この控除を受けるには、「適格請求書(インボイス)」の発行が必要になります。
インボイスは、国が定めた必要項目を満たした“正式な請求書で、従来の請求書とは書き方が異なります。
詳しくは国税庁サイトへ:インボイス制度について
フリーランスはインボイス登録すべき?
適格請求書発行事業者としての登録、いわゆる「インボイス登録」をすべきか迷っている場合は、以下のポイントを基準に判断してみましょう。
- 主な取引先が課税事業者である
- 今後、課税事業者との取引が増える見込みがある
- 売上が1,000万円を超え、将来的に課税事業者になる予定がある
上記のいずれかに当てはまる場合は、インボイス登録を行うことを検討すべきです。
判断に役立つ制度の背景や影響についても、補足しておきます。
売上が1,000万円以下のフリーランスは、これまで「免税事業者」として消費税の納税が免除されてきました。
しかし、免税事業者のままでは、インボイス(=適格請求書)を発行することができません。
取引先が「課税事業者(=消費税を納めている事業者)」の場合、こちらがインボイスを発行できないと、相手側が仕入税額控除を受けられず、税負担が増えます。
そのため、インボイス対応している事業者との取引を優先されるリスクがあり、特に新規案件の獲得に不利になる可能性も。
一方で、取引先が一般消費者や免税事業者ばかりであれば、インボイス登録を行わなくても、当面は大きな支障が生じないケースもあります。
大切なのは、ご自身の取引環境や今後の事業方針を踏まえたうえで、冷静に判断することです。

主な取引先が課税事業者なら、登録しておかないと敬遠されることもあるかもってことか~

そうです。でも、取引先が一般の人ばかりなら、必ずしも登録しなくても問題ない場合もありますよ。
請求書を自分で作成し、送付・管理まで行う際の主なステップは以下の通りです。
国税庁のウェブサイトや、会計ソフト会社が提供している無料テンプレートを利用すると便利です。
後述する必須項目を、漏れなく記載します。
作成した請求書は改ざん防止のためにPDF形式に変換し、メールで送るのが一般的です。
メール件名には、「【請求書在中】株式会社〇〇 ○月分ご請求の件」など、内容がひと目でわかる表現を使いましょう。
発行した請求書の控えは必ず保管し、入金状況を自分で管理します。
インボイス対応請求書の記載項目一覧
インボイス制度に対応した請求書(=適格請求書)を作成するには、従来の項目に加えて、新たに記載すべき項目があります。
以下のチェックリストをもとに、抜け漏れがないか確認しましょう。
- 宛名(取引先の正式名称)
- 発行者情報(氏名または屋号、住所、連絡先)
- 発行日(請求書を発行した日付)
- 請求書番号(管理のための任意の番号)
- 請求内容(商品・サービス名、数量、単価などの明細)
- 合計金額(消費税を含む合計額)
- 振込先(銀行名、支店名、口座番号、名義など)
- 支払期限(入金をお願いする期限)
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目である旨)
- 税率ごとに区分した税込金額と適用税率
- 税率ごとの消費税額
- 請求書の受領者(取引先の氏名または名称)
※インボイス(適格請求書)を発行するためには、事前に「適格請求書発行事業者の登録申請」を行う必要があります。
国税庁サイト:適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
テンプレートの活用と送付・保管の注意点
請求書をゼロから作成するのは手間がかかるため、インボイス制度に対応したExcelテンプレートの活用をおすすめします。
テンプレートにあらかじめ計算式を組み込んでおくと、数量や単価を入力するだけで小計・消費税・合計金額を自動計算できて便利です。
請求書を送付したあとは、控えを保存することが法律で義務付けられています。
とくにインボイス発行事業者が発行した請求書の写しまたは電磁的記録を7年間の保存が必要です。
保存時には、以下のようにファイル名を工夫すると検索しやすくなります。
ファイル名の例:2025-06-30_請求書_NO001_株式会社〇〇.pdf
さらに、Excelなどで別途「請求書管理表」を作成し、入金状況を一覧で確認できるようにしておくと、入金漏れなどのトラブル防止にもつながります。

請求書を自作するなら、登録番号や消費税額の記載など、インボイスの追加項目に注意ですね。

覚えることが多いですね…。保管も7年必要なら、ファイル名の付け方も工夫しないと。
請求書をExcelなどで自作する方法は、コストを抑えられる反面、手間やミスのリスクも伴います。
メリット・デメリットを理解したうえで、ご自身の事業スタイルに合った方法を選びましょう。
請求書を自作するメリット
まずは、自作のメリットから見ていきましょう。
- コストをかけずに作成できる
ExcelやGoogleスプレッドシートが使える環境なら、新たなソフト費用は不要。起業したばかりで経費を抑えたい方にとっては大きな魅力です。 - フォーマットを自由にカスタマイズできる
項目の追加・削除、レイアウトの調整、自社ロゴの挿入など、細かく自由に編集できます。 - オフラインで作業できる
あらかじめテンプレートをPC内に保存しておけば、インターネット接続がなくても作業可能。データをクラウドに保存したくない方にも適しています。
請求書を自作するデメリット
続いて、自作のデメリットや注意点です。
- 作成・送付に手間がかかる
金額入力、PDF変換、メール添付など毎回の手作業が必要。取引先が増えると作業量も膨大になり、本業に支障をきたすこともあります。 - 入力ミスなどのヒューマンエラーが起きやすい
金額や消費税の計算ミス、宛先の誤記、請求漏れ・二重請求など、信頼を損ねるリスクがあります。 - 管理が煩雑になりやすい
発行・送付状況や入金状況を手動で把握するのは大変です。管理表の更新漏れなどで、入金遅れに気づけないケースも。
これらのデメリットは、取引先や案件数が増えるにつれて顕著に現れます。
自作で対応する期間を経て、事業の成長に応じてクラウドサービスなどの導入を検討するのが現実的な選択です。

最初はコストをかけずに始められるのは大きいですよね。でも、デメリットも無視できませんよ。

案件が増えると、入力ミスや管理漏れが怖くなるね。信用問題にもなるし。

忙しくなると、ミスのリスクや時間のロスの方が、ツールの費用より高くつくこともあります。
請求書は、発行して終わりではありません。
法律で定められた保存期間に沿って、適切に保管・管理することがすべての事業者に求められています。
この章では、請求漏れ・入金漏れを防ぎつつ、税務調査にも落ち着いて対応できる管理方法のポイントを解説します。
法定の保存期間を守る
まず基本として、請求書の控えには法定の保存期間があることを理解しておきましょう。
個人事業主の場合、白色申告者の書類保存期間は原則5年(法定帳簿は7年)です。
青色申告者やインボイス制度にかかる適格請求書(発行・受領いずれも)は7年間の保存が義務付けられています。
この保存期間中は、税務調査などで提出を求められることもあるため、すぐに取り出せる状態で保管しておくことが重要です。
支払い状況で整理する
請求書管理の基本は、入金状況に応じて整理することです。
たとえば以下のようにステータスで区分しておくと、支払いの確認がスムーズになります。
- 「未入金フォルダ」: 発行済みで、まだ入金が確認できていないもの
- 「入金済みフォルダ」: 入金確認ができたもの
紙で管理する場合も、クリアファイルなどを活用してステータスごとに分けると、一目で状況を把握しやすくなります。
請求書の整理方法(紙・デジタル)
ファイリング方法は主に2パターンあります。
- 月ごとにまとめる
→ 月次の売上確認がしやすい。 - 取引先ごとにまとめる
→ クライアント別の取引履歴が追いやすい。
ご自身の業務スタイルに合った方法を選びましょう。
PDFなどで請求書を保存する際は、フォルダ分けとファイル名の工夫が重要です。
- フォルダ構成
→「年月別」や「取引先別」で分けると管理しやすくなります。 - ファイル名の例
→ 2023-11-30_請求書_NO123_〇〇株式会社.pdf
※発行日、請求書番号、取引先名を含めると検索性が向上します。 - 管理表の活用
→ Excelなどで「請求書番号」「取引先」「金額」「発行日」「支払期限」「入金確認」などを一覧化すると、請求・入金のチェックが簡単になります。

請求書は送って終わりじゃなくて、保管や管理も大事です。

特に保存期間は法律で決まっているので、フリーランスなら覚えておきたいポイントですね。

未入金と入金済みで分けたり、時系列でファイルを整理したりって、自分だけでやると手間がかかりそうですね。
これまで見てきたように、請求書を自作する方法には、手間・ミス・管理の煩雑さといった課題がつきものです。
そうした負担を解消し、本業に集中できる環境を整えるなら、クラウド請求書サービスの活用が最も効果的です。
ここでは、その具体的なメリットをご紹介します。
- 入力ミス・計算ミスを防げる
- 請求書の作成・送付がスピーディー
- ステータス管理で「もらい忘れ」防止
- インボイス制度や法改正にも自動対応
- 会計ソフトとの連携で業務を一元化
- 無料から使えるサービスも多い
とくに電子データでの保存が推奨される今、クラウド上での一元管理は実務面でも法的にも非常に安心できます。
入力ミス・計算ミスを防げる
クラウドサービスでは、金額や消費税の計算を自動で処理してくれるため、計算ミスや入力漏れのリスクを大幅に減らせます。
登録済みの取引先情報や品目マスタを使えば、転記ミスも起こりにくくなります。
さらに、必須項目の入力漏れがある場合はエラー表示が出るなど、人的ミスを防ぐ仕組みが整っています。
請求書の作成・送付がスピーディー
一度登録したデータをもとに、必要事項を入力するだけで請求書がすぐに作成可能。
毎月同じ内容ならテンプレートからボタン一つで発行でき、サービスによっては複数の請求書を一括で送信することもできます。
エクセルテンプレートへの手入力作業に比べて圧倒的な時短につながります。
ステータス管理で「もらい忘れ」防止
作成・送付した請求書は自動的に一覧で管理されます。
入金状況に応じたステータス(未入金/入金済みなど)が表示されるので、確認しやすいです。
リマインダーや督促メールの自動送信機能があるサービスもあり、入金確認の手間を削減し、もらい忘れを防止できます。
インボイス制度や法改正にも自動対応
2023年10月からのインボイス制度のように制度改正があっても、システム側が自動でアップデートしてくれます。
そのため、ユーザーは意識することなく最新ルールに対応可能です。
また、電子帳簿保存法に準拠した形式でデータが保存されるため、法令遵守の面でも安心です。
「制度変更について知らなかった…」と慌てて対応策を調べたり、考えたりする必要がないのは、大きなメリットです。
会計ソフトとの連携で業務を一元化
多くのクラウド請求書サービスは、クラウド会計ソフトと連携できます。
たとえば請求書を発行すれば、そのまま売上データとして会計ソフトに反映されるなど、帳簿管理や確定申告の効率化にもつながります。
クラウド会計ソフトと同じ会社が提供している請求書作成サービスを選べば、間違いありません。
- やよいの青色申告オンライン → Misoca
- freee会計 → freee請求書
- マネーフォワード クラウド確定申告 → マネーフォワード クラウド請求書
無料から使えるサービスも多い
「便利そうだけど費用が不安…」という方も安心です。
主要なクラウドサービスは無料プランや無料枠が用意されており、まずは0円で始められるものが多くあります。
事業の成長や月に発行する請求書の枚数に合わせて有料プランに移行できるため、導入のハードルは低く抑えられます。

クラウド請求書サービスの魅力は、請求書作成から管理、会計処理まで一気通貫でできることですね。

請求書だけじゃなくて、確定申告の準備まで楽になるのは嬉しいね。本業に集中できそう!
ここでは、インボイス制度に完全対応し、多くのフリーランスに支持されているクラウド請求書サービスを3つ厳選してご紹介します。
それぞれのサービスの特徴・料金プラン・対応ソフトなどを比較しながら、ご自身の事業スタイルに合った最適なサービスを見つける参考にしてください。
Misoca(ミソカ)

「弥生会計」でおなじみの弥生株式会社が提供するクラウド請求書サービスです。
私自身もMisocaを利用しており、同社の会計ソフト「やよいの青色申告 オンライン」と連携することで、請求業務から会計処理、確定申告書類の作成まで一気通貫で行える点に大きなメリットを感じています。
- 月10通まで完全無料で作成可能
請求書・見積書・納品書など、すべての機能を制限なく利用可能。取引先がまだ少ないフリーランスにとって非常に使いやすいプランです。 - 業務に役立つ管理機能も充実
請求書番号の自動発番や取引先マスタ管理など、請求書の整理・再利用に便利な機能が揃っています。 - 一括メール送信が可能
月末に複数の請求書をまとめてメール送信できる機能があり、請求先が多い方には特に便利です。 - インボイス制度に完全対応
テンプレートに沿って入力するだけで、適格請求書の要件をすべて満たすPDFが自動生成されます。 - UIがシンプルで操作しやすい
直感的に操作できるデザインで、請求書作成のハードルが低く、初めて使う方でも安心です。 - 有料プラン(月額1,000円台〜)も用意
10通を超える発行や郵送代行など、業務量の増加に合わせた拡張もスムーズです。 - 高い信頼性とユーザー評価
請求書ソフト部門での受賞歴もある信頼性の高いサービスです。
Misocaは、初期コストを抑えつつ、インボイス対応の請求書を簡単に作成したい方におすすめのサービスです。
また、やよいの青色申告オンラインなど弥生シリーズをすでに利用している方や、導入を検討している方には、連携面で非常に相性が良いです。
freee請求書

freee会計でおなじみのfreee株式会社が提供するクラウド請求書サービスです。
同社の「freee会計」と同じアカウントで利用でき、請求書作成と会計処理をシームレスに連携できるのが大きな特長です。
freee請求書は単体でも利用可能ですが、freee会計と組み合わせると効果バツグンです。
取引登録から請求書の発行、入金消込、確定申告までバックオフィス業務の一連の流れをfreee上で完結させることができます。
- 請求書は何通でも無料で作成可能
ユーザー登録をすれば、請求書の作成・編集機能は無制限に利用可能です(一部の機能、例:郵送代行は有料)。 - インボイス制度に完全対応
専用テンプレートに取引内容を入力するだけで、適格請求書に必要な項目を自動計算・自動配置。複雑なルールを意識せずに対応できます。 - freee会計と完全連携
会計ソフト「freee会計」(月額980円〜)を導入していれば、登録済みの取引先・売上データからワンクリックで請求書を作成できます。請求と会計のデータ入力を一元化でき、作業時間とミスを大幅に削減できます。 - 帳簿・確定申告まで一元管理
銀行口座やクレジットカード明細との自動連携、帳簿作成、確定申告書類の自動作成も可能。本業に集中できる環境が整います。 - 初心者にやさしいUIと豊富なテンプレート
画面操作は直感的でわかりやすく、freeeはユーザーサポートにも定評があり、初めてクラウド請求書を使う方にも安心です。テンプレート数は40種類以上。 - 法制度への対応もスピーディー
インボイス制度や電子帳簿保存法など、法改正に迅速に対応した機能アップデートが行われており、最新のルールに自動で対応できます。
freee請求書は、請求書作成だけでなく、経理・会計の効率化まで一気に進めたい方におすすめのサービスです。
また、すでにfreee会計を利用している方や、導入を検討している方には非常に相性の良いでしょう。
マネーフォワード クラウド請求書

マネーフォワード株式会社が提供する、クラウド型バックオフィス統合サービスの一部として利用できる請求書作成サービスです。
請求書はもちろん、見積書・納品書・領収書の発行管理まで対応。
さらに、クラウド会計・確定申告・経費精算・勤怠管理・電子契約まで幅広くカバーしており、事業の成長を見据えた総合力が魅力です。
- 月額800円〜の有料サービス(年払い時)
無料枠はありませんが、そのぶん高機能かつビジネス拡大に対応したサービス設計になっており、初年度無料のキャンペーンが実施されることもあります。 - インボイス制度に万全対応
テンプレートに従って入力するだけで、登録番号や税区分の自動反映・計算・レイアウト調整まで自動化。適格請求書の発行・受領管理の両方に対応しています。 - 請求業務を効率化する多彩な機能
取引先ごとの売掛金管理、入金消込の自動化、郵送代行(※切手代別途)など、請求〜回収までの流れをしっかりサポート。 - 他サービスとの連携で業務全体を一元化
クラウド会計・クラウド確定申告・クラウド経費などとスムーズに連携し、見積→請求→仕訳→決算申告までをワンストップで完結。日々の記帳から申告準備までを一貫して効率化できます。 - チーム・法人運用にも柔軟に対応
ユーザー権限の設定や承認フロー、複数人でのアカウント管理も可能。将来的に法人化したり、社内で経理体制を構築したりする場合にも柔軟に対応できます。 - 中長期の事業成長を見据えた設計
個人事業主からスタートアップ、中小企業まで幅広いニーズに対応。拡張性が高く、長く使い続けられる設計が大きな強みです。
マネーフォワード クラウド請求書は、請求書作成だけでなく、売掛管理や会計・経費精算など、事業全体の業務効率を本格的に改善したい方におすすめのサービスです。
将来的に法人化やチームでの運用を見据えているフリーランスやスモールビジネスの方にも、安心して使い続けられる選択肢となるでしょう。
自分に合ったクラウド請求書サービスの選び方
今回ご紹介した3つのクラウド請求書サービスは、いずれもインボイス制度に完全対応しており、安心して利用できる高品質なツールです。
そのうえで、ご自身の業務スタイルや将来の展望に応じて、次のような基準で選ぶのがおすすめです。
- コストをかけずに気軽に始めたい / 弥生シリーズとの連携を重視したい
→ Misoca(ミソカ) - すでにfreee会計を利用中、または導入を検討している / 請求書を月に10枚以上発行する
→ freee 請求書 - 機能の豊富さ・中長期の事業成長・法人化も視野に入れている
→ マネーフォワード クラウド請求書
請求書の発行枚数や、すでに使用している会計ソフトとの連携可否などを踏まえて、まずは無料で試せる範囲から導入してみるのがおすすめです。
使い勝手を実感したうえで、有料プランへの移行を検討していくと良いでしょう。

どのツールを使うかは悩みどころですが、まずは「月に何通くらい請求書を出しているか」を考えると、選びやすくなりますよ。

なるほど。今は発行枚数も少ないし、まずは手軽に始められるものから使ってみようかな。

事業が大きくなったら、機能が多いものに乗り換えるのもアリですし、段階に応じて使い分けるのがコツです。
フリーランスにとって請求書の発行は、報酬を得るうえで欠かせない大切な業務です。
特にインボイス制度の開始により、記載項目や保管義務が増え、より正確で効率的な対応が求められるようになりました。
結論として、請求書の作成・管理はクラウドサービスを活用して効率化しましょう。
無料または少額のコストで、作成ミスや管理漏れのリスクを減らし、安心して業務に集中できます。
特にインボイス対応では、記載漏れや計算ミスを防げる点でクラウド型は圧倒的に有利です。
会計ソフトと連携すれば、請求から確定申告までを一貫して効率化できます。
実際に私もMisocaと連携させることで、経理作業が格段にラクになりました。
請求書は最初こそ不安でも、ポイントを押さえ、便利なツールを活用すればすぐに慣れます。

作業を効率化すれば、本業にもっと集中できます。自分に合うツールを、うまく活用していきましょう!